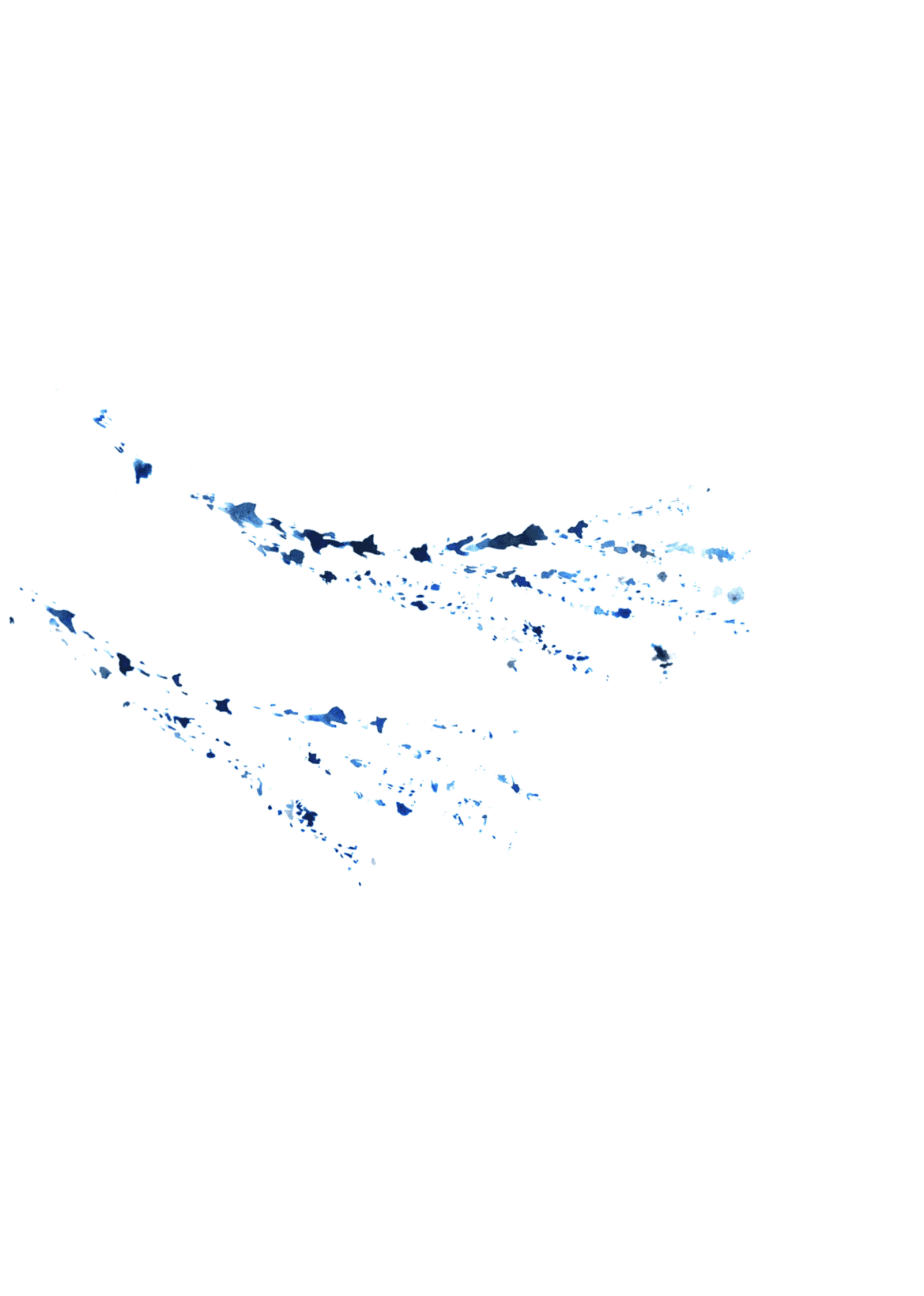はじめて下北山村の地を踏んだのは、3年前。
この村で「学生団体まとい(以下、まとい)」のメンバーとして活動してきて、春からは社会人となる。村に関わる理由だった「学生」という肩書きがまったく書き換わる。それを前に、「まとい」としてのこれまでを、特に大学4年生の今の視点から振り返ってみたい。
「地方」への関心
自分は東京生まれ東京育ちで、「ふるさと」がない、いわゆる「ふるさと難民」に該当する。

家庭の関係で盆正月に帰省するところはなく、学校の関係で近所に友達はいない。幼いころに虫取りをした森、家族で収穫体験をした畑、学校帰りにネコが日向ぼっこしていた空き地。近所の思い出の場所は、次々と宅地や駐車場に変わっていった。
右肩上がりの時代なら、「寂しくともそんなもの」と思ったかもしれない。しかし物心ついたときから、日本は「失われた◯◯年」の中にあり、「少子高齢化」「人口減少」の時代であった。地方では人口が減り続け、シャッター商店街や耕作放棄地などの問題が深刻であるという。
一方で自分の周りは、人が増え家が増え、数少ない思い出の風景もアスファルトに埋められてゆく。小さいころから、そんな状況になんとなく「違和感」を感じてきた。それが地方や地域への関心の原点になっている。
下北山村との出会い
大学に入学後、自分のまったく知らない「地方」について知りたいと思い、さまざまな講義を受講した。そのうちのひとつで出会ったのが、この「きなりと」1本目の記事を執筆した松村萌音だった。

自分と同じ、東京生まれ東京育ちで、地方への関心を持っていた。だから同じ講義を受講し出会ったのだが、自分とは決定的に異なる点がある。彼女は非凡な行動力をもっていた。誰かに勧められたわけでも、もちろん周囲の誰かがしているわけでもないのに、雑誌に掲載されていた講座「むらコトアカデミー」に自ら応募し、参加していた。
下北山村に、今後も学生主体で継続的に関わりたいと考えている。だから一緒に活動してみない?
同じく授業を受講していた永尾と二人、松村からそう声をかけられて、「地方」を知りたかった好奇心とともに、新しく何かを生み出せるかもしれないという可能性も感じ、二つ返事で誘いを受けることにした。
そうしてはじめて下北山村を訪れたのが、大学1年生の12月のこと。もう3年以上も前になった。

初訪問のときから、役場の方をはじめ、いろんな方と出会い、移住体験施設「むらんち」の立ち上げをはじめ、いろんな経験をさせてもらってきた。「地方」への理解も深まったし、林業や建築、暮らしなどのちょっとした知識も得られた。なによりも、何回も訪問するなかで構築されてきた、顔や名前のわかる関係は、何にも代えがたい財産となった。



そうして多くをもらってきて、自分たちも何かお返ししたいとずっと思っていながら、でも具体的に何をすればいいのかわからないまま、コロナウイルスが広まって訪問できなくなり、あっという間に大学4年生になってしまった。
今、自分にできること
訪問するたびに、毎回のように村の人に言われることがある。
大学生が村に来て、何かしようとしてくれるだけでありがたい。
村には高校がなく、高校生になったら子どもはそのほとんどが村を出ていくことになる。したがって、村には高校生や大学生がいない。確かに若い世代が、遠路東京からやってきて何か活動しようとしてくれるのは嬉しいことかもしれない。
そのことを思い返したとき、残り短くなった学生生活のなかで、少しでも何かお返しをしたいという気持ちが強くなる。卒業までの時間もコロナも、どうしようもない制約として立ちはだかる中で、自分がどうすべきかの考えは自然と整理がついた。
立ち上げた「学生団体まとい」を、自分たちが卒業した後もきちんと続くようにする。すなわち、継続的に学生がやってきて村の人を巻き込みつつ何か活動を試みる、盛り上げようとする。そういう環境を作ることが、自分が今できる最大限のお返しでもあり、「まとい」を、そして「むらんち」を作った1人としての責任ではないか。そう思った。
ゴールではなくスタート
「まとい」を続けようにも、続けてくれる人がいなければ元も子もない。サークルやバイト先の後輩に声をかけたり、「まとい」結成のきっかけとなった少人数の講義に勧誘に行ったりした。
そうして幸いにも新メンバーを数人集めることができ、2021年9月にはコロナが落ち着きつつあるのを見計らい、新メンバー2人とともに村を訪ねた。

1年半ぶりのこの訪問では印象的なことが多かったが、中でも「むらんち」を見たときの感覚は特に記憶に残っている。
実はこのとき、2年前に自分たちで話し合ったりアイデアを出したりして、はじめから携わってきた空き家が「むらんち」として生まれ変わった姿を、直接目にしたのは初めてだった。パソコンの画面越しに見たことはあったが、いざ直面すると不思議な感覚が湧きあがってきた。ゴールとスタートを同時に踏む感覚である。
改修に自分も含めいろんな人が関わり、その数だけいろんな想いも思い出も詰まった場所が生まれたことが、ある種の達成感―ゴールのようでひたすらに感慨深かった。

一方で、「むらんち」という「施設=ハード」が完成したからこそ、これから「どう活用するのか=ソフト」をどうしていくのか、というスタートラインに立った気分になった。
ハードを作るだけ作って活用できずに苦労する、というのは地方活性化の事例でよくあることだ。このとき既にワーケーションでの利用は始まっていたが、それは村(役場)としての活用方法であり、「まとい」としての活用方法を真剣に考えなくては意味がない。
完成がゴールではなくスタート。
ありがちな言葉で、頭ではそうだろうと理解していても、実際に「むらんち」を目にしたときに感じたこの感覚は、頭での理解が全く浅はかであることを痛感させた。
訪問するまで予想していなかった感覚であるとともに、対面で現場を感じる重要性を改めて認識するきっかけにもなった。
尽きない新たな出会い
「まとい」として活動してきた3年余りは、人との出会いに溢れていた。
役場、地域おこし協力隊、NPO、農家さん、パン屋さん、その他にもたくさんの村民の方々…。下北山村という1つの地域に暮らす方々にも、多様なバックグラウンドがあることを知り、それだけの様々な考えや知識を学んだ。どの出会いも忘れがたく、これからも大切にしていきたいと思っている。


また、村と関わるなかで、たくさんの村外の方たちとも出会った。
空き家改修のときには、大阪工業大学の講師・学生、となり町の大工さん、カメラマン、コーディネーターの方などだ。自分たちと同じように村の外から関わりながら、世代も、暮らす地域も異なる方たちとの交流は、やはり自分たちにはない考えや視点をもたらしてくれた。
村に住んでいるわけではなく、だからこそ村の方々以上に奇跡的で貴重なこれらの出会いも、大切に心に留めておきたい。

正直、これだけ有意義で心も満たしてくれるような出会いができて、十分お腹いっぱい、という気持ちがなかったわけではない。しかし、今年また、別の角度での出会いがあった。「まとい」に共感して加わってくれたメンバーたちである。
9月の訪問後も、同期は自分だけで他は新メンバーばかり、というような訪問をしてきた。
同期が自分だけだったのは、コロナで人数を抑える必要がある中で、車の運転ができて比較的ひまだったから、というしょうもない理由からである。もちろん、なかなか村に行くのが難しい状況の中で複数回訪問できるのは嬉しく楽しみだったが、毎回気心知れた仲間と行けないのは「ちょっとさみしいなあ…」、という気持ちもあった。
ただ、改めて考えると、他の同期の仲間よりも長い時間を新メンバーと過ごすことができたのは、ある意味幸せなことだったと感じている。

「むらんち」を作ったこと、「まとい」として積み重ねてきた活動に、その過程を直接見ていない新メンバーたちが共感してくれた。ほぼ同世代の第三者が、自分たちのやってきたことを認めてくれて、その想いを繋ごうとしてくれる。
そんな出会いは、それまでの村内・村外の方々との出会いとは違う意味で嬉しくありがたく、想像以上に大きなインパクトだった。遺志を継ぐ人を見つけ、安心して成仏する。大げさだが、そんな気持ちに近い気もする。
幸か不幸かコロナのせいで、他の同期よりも深く新メンバーと関ったことで、そんな嬉しさを人一倍に感じることができたのではないかと思う。学生最後の1年にしてまた新鮮な感情・感覚を得られ、活動していてよかったと、何度目かわからないが改めて思う機会となった。
「まとい」をつなぐ
下北山村と関わるなかで、新たな学びや出会いを得ること。
「まとい」のメンバーで話し合って決めた、「まとい」の活動理念である。はじめの動機こそ様々あれど、「村と関わるなかで、新たな学びや出会いを得る」のはみんなに共通していた経験であり、継続的に関わる動機にもなってきた。

曖昧ともいえる「新たな学びや出会い」の中身は、ここに書ききることができない。
出会いに絞ってそれを大きく分けたとしても、村に暮らす人、村外から関わる人に加え、「まといを引き継いでくれる仲間」という新しい出会いが今年あった。そしてその出会いが、また新たな気づきや学びをもたらしてくれる。
初めから得ようとするものを決めつけるのではなく、関わっていくなかで自然と何かを得ること。そんな、ある種の「曖昧さ」が「まとい」の良さでもあり、あるいは本質にもなっている。このことを感覚的に理解してくれる学生がいて、「まとい」の活動が続いてゆけば、下北山村にとどまらず、大げさだが日本が少しは良くなるのではないかとも思う。
だからこそ、新メンバーとの出会いは嬉しく、想いの継承が続いていくことを願っている。
下北山村とは。そしてこれから。
生まれても育ってもいないのにこれだけ長々と語れる、下北山村とはいったい何なのか。

「第二のふるさと」と答えるのが「正解」そうだが、「ふるさと」という感覚がよくわからないし、想像する「ふるさと」ともちょっと違う気がする。一言でまとめるのは非常に難しいが、いてくれるおかげで自分を成長させてくれる、慕いたくなる存在だと感じることはある。
直接にいろんなことを教えてくれるだけでなく、「村外」との出会いや学びももたらしてくれた。それが自分の考えを豊かにして、成長させてくれた。とにかくいろんなものを授けてくれたので形容しがたいが、本当にかけがえのない存在である。
春からは環境が大きく変わり、自分は社会人となる。必然的に下北山村との距離も開くことになるだろう。慕いたくなる存在から遠ざかることは、少し寂しい。そんな状況を前に、当然社会人になる緊張感もあるが、村との関わりでは少しワクワク感もある。
まとい1期生のような存在として、初めてのOBOGの1人となる。下北山村の「関係人口」の1人としても関わっていくことになるが、自分たちのような経緯での関係人口は前例がない。他地域での事例を見ても、関係人口の地域への関わり方に決まった枠はなく、それが難しさでもある。

これからはどのように下北山村と関わっていくことができるだろうか。
前例がないからこそ難しさもあるが、そこには新しく何かを生み出すワクワク感もある。初めて下北山村に来たときに感じた感覚を、3年越しにまた味わえている気がする。

- 木村誠之
- Kimura Masayuki

東京都出身。慶應義塾大学在学中。2022年春に卒業予定。大学2年時より、大学同期の松村萌音らと共に「学生団体まとい」のメンバーとして下北山村での活動を開始。食農に関心があり、長期休暇には泊まり込みで農家の手伝いに行くことも。