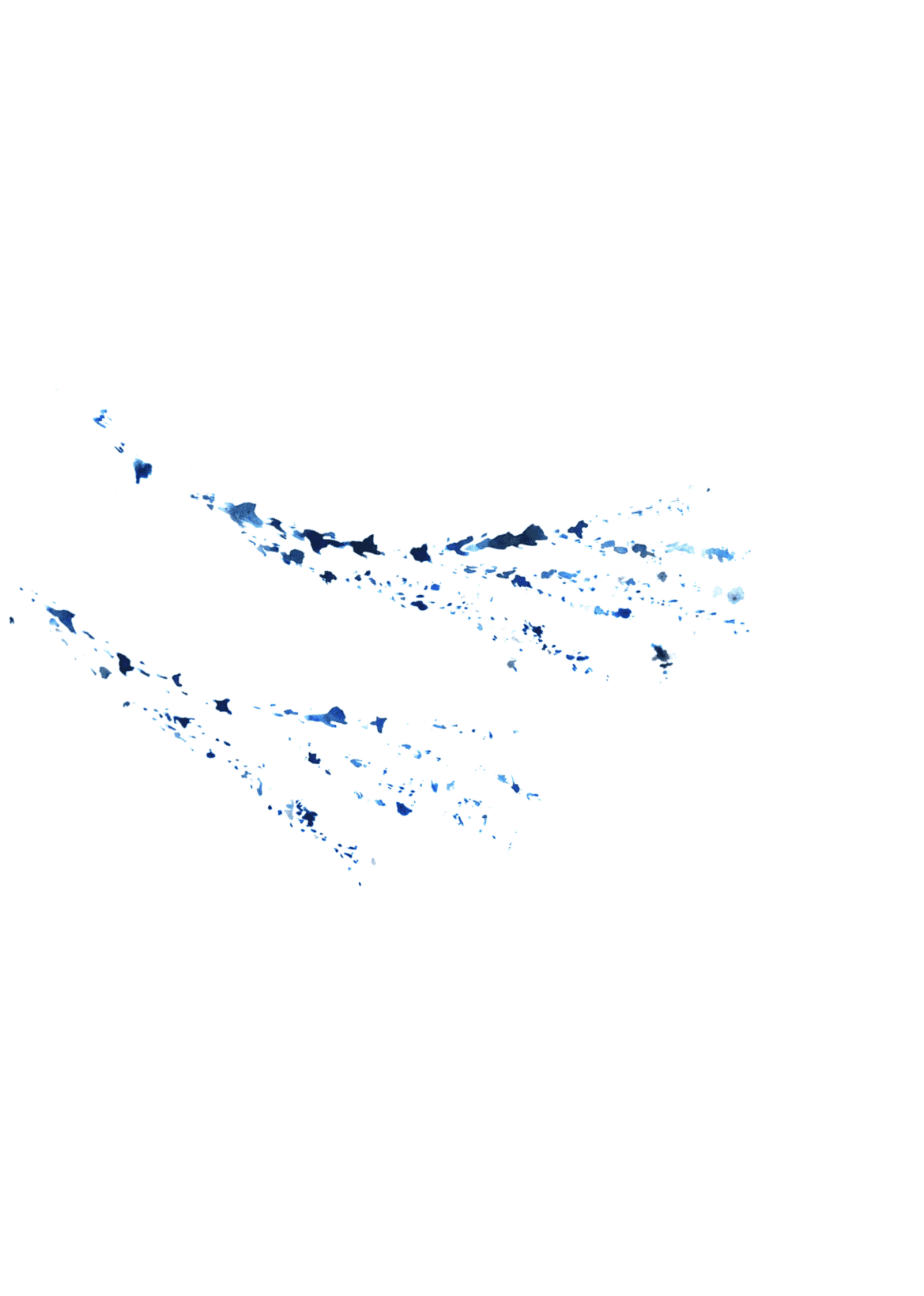私の家からは山が見えない。目に映るのは乱立する建物たち。
私の家の裏には川がある。でもそこで魚が泳ぐのを見たことがない。
都内の大学で経済学部に学ぶ私は、「幸せとはなにか」について考えさせられる機会が多い。経済学の世界では「幸せ」をシンプルに「効用」と呼ぶが、この効用について、経済学を学ぶ誰しもが知る次のような定理がある。
各個人が自由に利益を最大化する生産活動に従事すると、各個人の効用の大きさの観点から社会的に望ましい結果(パレート最適という状態)に必然的に到達する。
資本主義的な利益追求活動を肯定しうる定理なのだが、現実には強欲な生産活動は公害や気候変動問題など、効用を低下させる数多の問題を引き起こしてきた。見逃されているのは他者や自然、つまり周囲の環境への配慮の心だ。
ドイツ出身の経済・環境学者、カール・ウィリアム・カップは、自己利益の最大化に資する経済活動が、周囲の環境に対して費用(cost)を転嫁(shift)するcost shiftingを生み出していると整理した。皆がcostをshiftしあう社会では、山は無造作に切り開かれ、川には躊躇なく汚水が流された。先人が土地に残してきた履歴は、都市開発の波に埋め立てられてしまった。
人生の半分以上を東京で過ごした私にとって、下北山での暮らしはオアシスだ。この村は本当に豊かだ。美しい山があり美しい川があり、その恵みを受け取る人々は雄大な自然に帰依する。そこにあるのは、自然と人間の双方向のやり取り。東京に住む私たちが忘れてしまったもの。

以前、よそ者という立場であるにも関わらず、浦向の地区祭に参加する機会をいただいた。かつて林業で栄えたこの地区では、今も山の神様に感謝の祈りを捧げる。クライマックスの餅撒きでは、地区のお母さん方が朝についたばかりの栃餅(栃の実を餅米と蒸してつくる餅)をこれでもかといただいた。一度に受け止めきれないほど温かい、山の恵みと村民さんの優しさに触れた。

また村のある方は、「西ノ川がなくなると、下北山は下北山でなくなる」と仰った。アマゴやアユといった川の幸を生み出し、幼少期から身近に接してきたその川は、もはや下北山に住むというアイデンティティの根幹を成している。滞在中に村民さんがおすそ分けしてくれるアマゴの甘露煮は、村に行く楽しみのひとつだ。

この自然と人間の密な交流は、下北山に代々暮らしてきたご先祖様が守り続けてきたものだ。昔の人々が残した知恵や慣習は、そのまま履歴となって蓄積される。それを受け継いだ村の人々は、美しい自然が皆の生活の基盤となっていることをよく理解し、丁寧に、丁寧に管理する。自然を、他者を、思いやる気持ちで、日々の生活を営んでいる。私が常々感じていた村の豊かさの正体は、きっと人々に根付くこの心だ。私が常々、村で感じていた「効用」は、きっとこの心と触れ合う瞬間に生まれるのだ。
大峯奥駈道が南北に沿う下北山は、古くから修験文化の震源地でもあった。修験道が拠り所とする天台本覚論は、周囲の環境の至るところに仏様を見いだす「山川草木悉有仏性」を説いている。下北山村民のマインドの根幹に触れるべく、1300年に渡って修験者を迎えてきた前鬼山小仲坊から、下北山の頂、釈迦ヶ岳を目指した。
息を呑むほど青く澄んだ川、恐怖を感じるほど力強くせり立った岩壁、遥か遠くまで続く山嶺……。


厳しく雪が吹き付ける登山道にあっても、自分より遥かにスケールの大きい存在に見守られている感覚が確かにあった。息も絶え絶えに辿り着いた山頂。柔和に微笑む釈迦如来像を前に、思わず頭を垂れた。

あまりに遅い自己紹介となるが、私は現在、下北山で中学生の教育支援に関わっている。高校受験対策に焦点をおいた講義をしているが、子どもたちとの交流の中で、私たちも学ばされることは多い。

雄大な自然に抱かれて、彼ら彼女らは本当にいろんなことを覚えている。教え子に下北山ならではの「秘密基地」に連れて行ってもらったことは、一生の思い出だ。私にとってのユートピア、下北山で時間を過ごす「効用」を味わいながら、これからも村民さんとの交流を楽しんでいきたい。
- 森藤啓介
- Morifuji Keisuke

2002年、東京生まれ。一橋大学経済学研究科修士1年。中高6年間を奈良県で過ごしたことをきっかけに、奥大和地域に関心をもつ。大学2年次より学生団体まといに所属し、村内中学生の教育支援などに関わる。専攻は環境経済学・開発経済学。