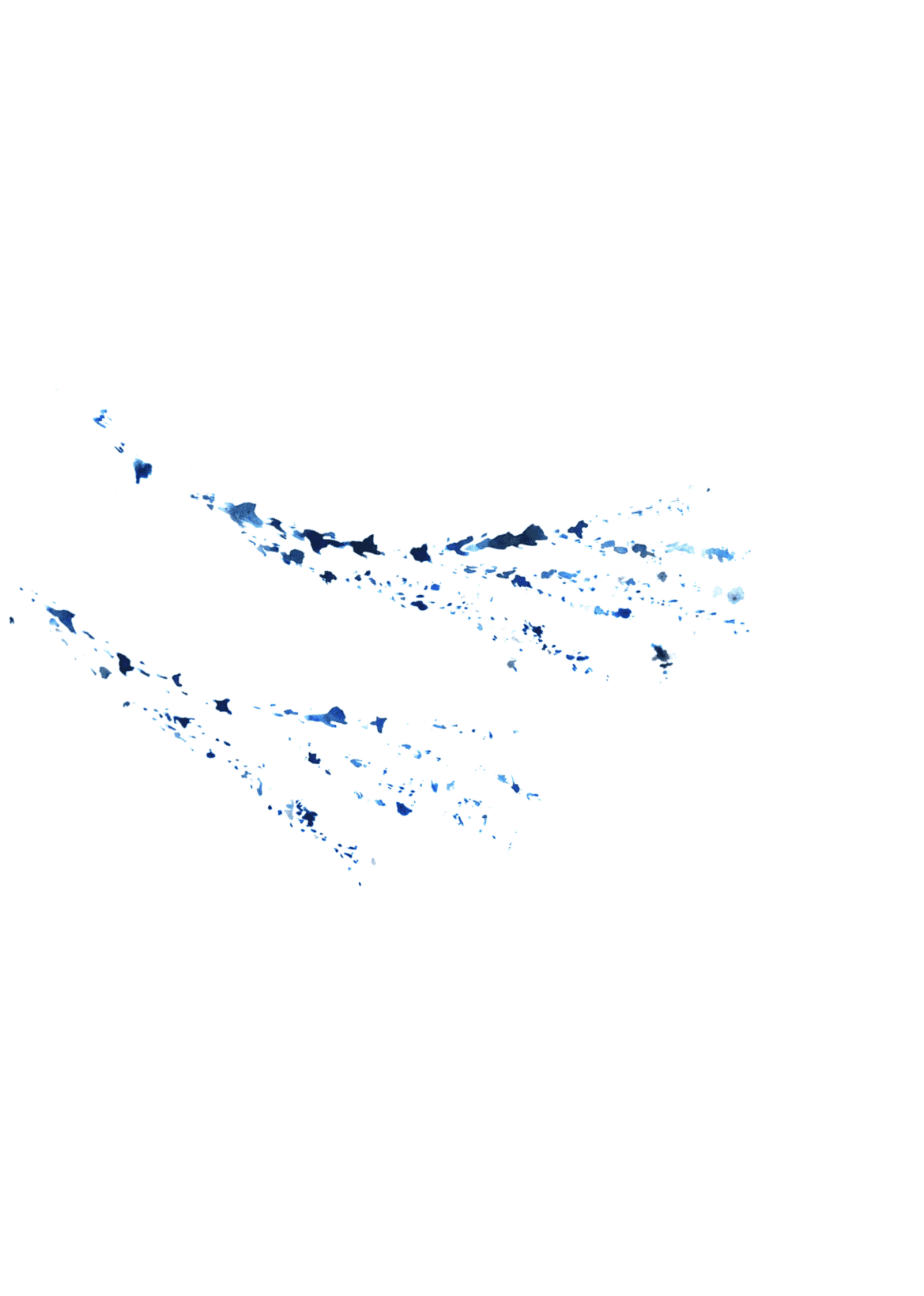ふるさとをなくしてしまった。という思いが、長い間ずっと、わたしの胸の内にありました。
わたしが生まれ育ったのは、東京です。といっても、わたしたちが暮らしていた家はいわゆるコンクリートジャングルではなく、のどかな環境にありました。裏庭で柘榴や桃をもいだり、庭石に登ったり、近所のお寺の境内を走り回ったり。
お盆やお正月になると、親戚が大勢集まります。母や祖母が大鍋でごちそうをこしらえ、わたしたちも手伝いに追われます。台所はおいしそうな匂いで満たされ、広間では冗談に笑う叔父たちの声が聞こえています。忙しいながらも、久しぶりにいとこたちに会うのが楽しみで、「毎月お正月があればいいのになー」と思ったものでした。
今、あの町に降り立っても、当時の思い出を共有できる人も、家も、光景も残っていません。町並みは変わり、見知らぬビルが立ち並んでいます。根気強い遊び相手になってくれた石や木々も、懐かしい我が家もありません。
帰る場所はもうないんだなあ。という、迷子になったような心持ち。だから、ずっと思っていました。「わたしにはもう、ふるさとがない」と。けれども下北山村で、その考えをあらためる出来事がありました。

下北山村を案内してくださったのは、和田英樹さん。この村で生まれ育ち、大阪で働いたあと戻ってきて、現在は村役場に勤める55歳。偶然ですが、わたしと同い年です。
和田さんは、生まれ育った集落を歩きながら少年時代の思い出を教えてくれたのですが、それがもう、なんとも羨ましい話ばかりなのです。
ここらで水泳というたら、プールやなくて川でしたよ。友だちと橋桁の上から飛び降りたり、川底の大きな石を抱えたまま水の中を歩いてみたり。学校の行き帰りも楽しくてね。通学路でワラビやゴンパチ(いたどり)をとると、それが晩飯のおかずになるんです。
サッカーチームに入っていたからサッカー少年やったけど、近所の子らとは野球もしましたね。今、歴史民俗資料館のあるあたりは、田んぼやったんです。稲刈りの終わった田んぼで走り回ったり、木を拾ってきてボールを打ったり。そうやって、自分たちで遊びを見つけ出すことが面白いんですよ。
子どもたちだけではありません。
大人たちも負けずおとらず本気で遊んでいたそうです。
昔、このあたりは青年団が活発で、ちょっと古い時代には自分たちで劇をつくってあちこちを回っていたそうです。そうやって村の人を喜ばせたかったんですよね。
そういえばうちのおやじが盆踊りのときに変な格好をしていてね。「恥ずかしいな」と思ったけれど、あれも人を喜ばせたいからやっていたことやったんやね。
おやじは山仕事をしていて、仕事が終わると家の玄関先で、仲間と車座になって酒を飲みながらワイワイ喋っていたもんです。
周りと一緒に楽しみたいという気持ちが、さまざまな遊びを生み出します。
それでも、時には失敗することもあったそうです。
僕、校庭でうっかり五寸釘を踏んだことがあってね。ムカデの油漬けを塗ってもらって治しました。どこの家にもあったんですよ、ムカデの油漬け。あのときはおばあさんがおまじないしてくれたなあ。そんなことも覚えています。
あの時代は、失敗しても許されたんですよね。それに、失敗から学んでいくことも多かったと思います。
たとえば川で石をむやみに投げたら、周りの人を傷つけるでしょう。せやから、どうしたら人に当てずに遊べるかを考えるようになる。人が近くにいたら危ないけど、離れていれば投げても当たらない、って。そうやって、距離感覚を学んでいくんですよね。
痛い思いをしたり、汚れたり、つらかったり。そういう体験も、ただ「しんどい、つらい」ちゅうだけやなくて、そこから学ぶものがあってね。なんというか、生きていく知恵ちゅうのかな。
僕が生まれてはじめて稼いだのは、新聞配達でした。まだ小学生のときでしたが、同級生の家が新聞屋でね。学校が終わってから地区の家を回るんです。 雪や雨の日はつらかったけど、そこから学ぶことも沢山ありました。

新聞配達をして、もらった小遣いで、アイスや花火を買うてくるんです。集落の入り口に日用品を売っている店があってね。今やと花火はセットで売ってるもんやけど、その店ではバラで売ってる。そのなかから自分の好きな花火を買うて遊ぶんです。
通学路でとってくるワラビやゴンパチだって、お金を出したら簡単に食べるものを買える生活でのそれとは違う。今は熊野市まで買い物に行けるけど、あの頃のここらへんは、野菜なんかつくれるものは自給自足が基本でしたね。自分で食べるものを見つけるちゅうことが、一日一日を生きていくうえで当たり前やった。そんな家で育ちました。
そういう日常のなかに、大切なことがあったんちゃうかなあ。
思い出話のひとつひとつが、キラリキラリと輝いています。しかも羨ましいのは、今も目の前に思い出の山があり、川があるということ。子どもの頃の自分を知っている人たちが、今も近所に暮らしていること。
思わず「いいなあ。ふるさとが残っていて」とつぶやくと、和田さんは「でも、変わりましたよ」と言いました。
今の景色は、僕らが子どもの頃とは全然違うんですよ。川の水の量が少なくなったし、ほら、今は砂底になっているでしょう。川幅だって全然違います。


集落にあった店はなくなってしまった。通学路だって、今はバスで往復するから、昔みたいな楽しみは少ないですよね。僕らの思い出にあるようなものは、ほとんどがなくなっているんですよ。
わたしは衝撃を受けて、しばらく言葉が出なくなってしまいました。川のほうから水音が聞こえてきます。山のほうで鳥の声がします。集落では水路の石積みからサワガニが顔をのぞかせ、民家の納屋にはよく使い込まれた農具が並んでいます。
こんなに自然の豊かな場所でも、こんなにゆっくりと時間が流れていても、ふるさとは刻々となくなってしまうのか。
そのとき、ブーンブーンとモーター音が響いてきました。小高い丘のてっぺんの、民家の庭先で、男性が草刈り機を動かしています。一心に作業していて、こちらには気がついていないようです。
「あ、いとこの兄ちゃんや。普段は愛知で暮らしているんやけどね、こっちに帰ってきとるんか。ちょっと声をかけてみよう」と和田さんは言うや、「ホウ! ホウ!」と声をあげました。
それはとてもよく響く声でした。叫ぶとも違う、大声を上げるのとも違う。高く鋭く、咆哮に近い発声でした。
ホウ! ホウ!
これは山仕事の声ではないか、と思いました。
こんなとき、「おーい」と普通の声をあげても、草刈り機のモーター音に消されてしまいます。かといって背後まで近づいて相手の肩を叩けば、驚かせてしまって互いに危険でしょう。けれどもこうして自分の身体の内側に声を響かせ、楽器のようにあたりにとどろかせれば、誰も傷つかない。安全かつすみやかに、意思疎通ができるのです。なんという豊かな知恵!
はたしてその声を耳にした男性はモーターを止め、振り返って和田さんの姿を認めると笑顔を見せました。
和田さんは山仕事についたわけではありません。役場の職員です。それでも和田さんは、お父さんから教わった山の学びを無意識のうちに活かしているように見えます。
たとえば、救急車のサイレンが聞こえてきたとき。和田さんは「どこの家の誰が具合を悪くしたのだろう」と耳をそばだてたあと、「このあと自分はどう動いたらいいか」と考えて、準備をするそうです。
村で起きていることは、どんなことも他人事ではない。何かしらの形をとって、自分の日常や仕事にも関わってくる。和田さんにはそういう意識があるのでしょう。それは山仕事の、「どの木を切ったらどこに日が差し、水の流れが変わっていくのか」という知見や、「山仕事は命にかかわるから、いつでも全神経を張り巡らせて仕事にあたる」という意識ともつながっているように思えます。
ふるさとは、消えたわけではない。
そう、思いました。目に映る景色は消えても、姿形を変えても、懐かしい人々がこの世を去っても、ふるさとは和田さんの身体に場所を移して生きている。そして今でも折々に知恵を授け、力を貸してくれている。
そういえば和田さんは、こんなことも言っていました。

僕には、「地域の文化を忘れてほしくない」って思いがあるんやね。たとえば通学路を歩けば、ワラビが摘めることとか、そういうちっぽけなことを。それは誰かの人生のなかの1%か2%にしかならんかもわからんけど、こういう山のなかで暮らす文化の特色は伝わっていってほしい。
この言葉を聞いたとき、下北山村がわたしに語りかけているような気がしたのです。
この村の歴史や、ここで生きてきた人や、山や川……つまりはこの村が、和田さんの身体を借りて「これでいいのか?」と問いかけたり、「よし、いいぞ、いいぞ」と励ましたりしている。
和田さんだけでなく、おそらくこの村に生きてきたひとりひとりの内にあるのでしょう。懐かしい場所の記憶や、村に降り積もった知恵は、「生きよ! 皆、生きよ!」と揺さぶってくる。だからわたしたちは、迷いながらもどうにかこうにか道を間違わず、刻々と変わる世界の中で、いまだ知らぬ未来を生きることができるのではないかな。

ふるさとをなくしてしまったなんて、わたしはもう思わないでしょう。
目に見える形では存在しないけれど、ふるさとは自分の中にたしかにある。わたしが生きれば、ふるさとは生き続ける。産土(うぶすな)が語りかける「生きよ!」という声に耳をすませながら、今とこれからを作っていけばいい。そのことに気づかせてくれた下北山村という場所に感謝しています。

—photo by togo yuta , akashi kensuke
- 渡辺尚子
- Watanabe Naoko

東京生まれ。学生時代は舞台美術研究会に所属し、ライブハウスや小劇場の照明にあけくれる。卒業後、出版社勤務を経て、フリーランスの編集者、ライターとなる。現在は東京西郊の、野鳥が集まる雑木林の近くに暮らしながら、市井の人々の生活を記録している。「暮しの手帖」で連載中。