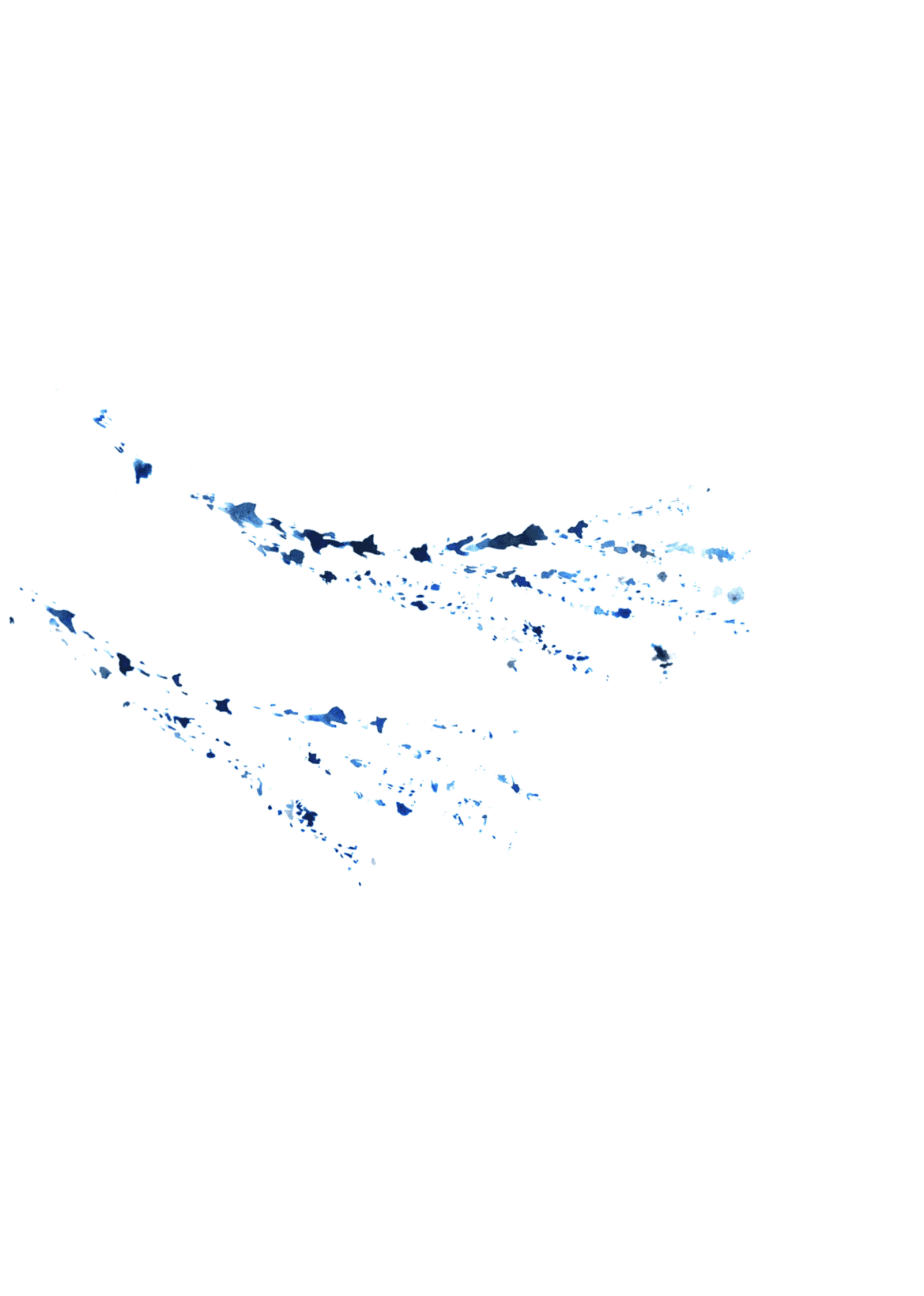家族で下北山村から引っ越して1年になる。
今回記事を書くお話をいただいて、村に住んでいたときに撮っていた写真の整理を始めた。深緑の森、太陽の光で表情を変える川、村のおばあちゃんに抱っこされてうれしそうな長男。村での生活はかけがえのない時間で、今でも思い出すと胸が温かくなる。

3年前の2019年、さくら祭りの日に下北山村に移り住んだ。夫が診療所に医師として派遣されたため、家族で村に引っ越すことになったのだ。
夫との出会いは看護学生時代に参加した僻地医療の勉強会だった。わたし自身も僻地での医療について興味があったし、夫の僻地への転勤が決まったときは二つ返事でついていくことにした。
引っ越してきた家は築30年の平家だった。
長らく誰も住んでいなかったらしいが、畳も新しいものに替えてくれており、部屋いっぱいに井草の香りがした。当時、生後3ヶ月だった長男も初めての畳が気に入ったようで、足をバタバタとさせて喜んでいた。夫とゆっくり話すのも久しぶりだった。「これからの生活が楽しみだね」って話と、「見知らぬ土地で育児するのってちょっと不安だね」って話をした。
今はすっかり年子兄弟のお母さんとして毎日家事と育児をこなしているが、初めての子育ては毎日知らないことの連続だった。「赤ちゃんのサインを見逃さないようにしましょう」って簡単に言うけど、全部が大事なサインのような気がした。常に見逃さないように気を張っていたし、子どもと2人きりで過ごすと息が苦しくなることがあった。
窓を開けるとギギギと音が鳴った。
入ってくる空気がすっかり春の匂いで、子どもが生まれてから随分と外に出ていなかったことに気がついた。

村での育児は大袈裟でなくのびのびと楽しんだ。
夏の暑い日は冷たい川の水に足をつけたり、風の気持ちいい日は裸足で草っぱらに寝っ転がったり。癇癪を起こして泣いている我が子の声がやまびこしているのを聴きながら、野生動物がみんな逃げていきそうだなとか考えていた。
村にいるときは毎日お出掛けした。
「コワーキングスペースBIYORI」に行ったら村の誰かに会えたので、長男が喋り始めたり歩き始めたときは自慢しに行った。

悩みがあると診療所に行って、夫や診療所のスタッフ達と一緒にランチをしながら話を聞いてもらった。小腹が空いたら「たもとパン」に、卵サンドやあんパンを買いに行った。たまにちょっと焦げたあんパンをサービスしてくれるのがうれしかった。

ママ友と車で山道を走り、片道40分かけて海を見に行ったり、尾鷲のキッチンカーにも月に一回通って、海を見ながらホットサンドやおでんを食べた。予定は決まっていなかったけど、その日の天気や気分で子育てをしていた。

家の周りを散歩することもあった。すれ違った村のおばちゃんが「赤ちゃんは村の宝やからねぇ」と言いながら、ニコニコして長男を抱っこしてくれた。抱っこしていた長男の重さ以上に心が軽くなったのを覚えている。
わたしは芸大在学中に挫折している。小さい頃から絵を描いてご飯を食べていくのだと信じていた。しかし、その夢は見事に打ち砕かれた。わたし自身の中身が空っぽで、いざ作品を作る環境になると何も描けなかったのだ。
でも、村に来てから細々と絵を頼まれるようになった。自分の作品が誰かに必要とされて喜んでもらえるうれしさもあったし、物を作る理由って、結局誰かのためなのだと思った。
あるときから、芸大時代には一度も取り組んだことのなかった刺繍を始めるようになった。一針一針縫う過程で、作品の意味などを考える時間がたくさんあって、自分のペースで制作できる点が魅力だ。

村を出た今でも続けているが、受け入れてもらえる居場所があるということが、わたしの制作の拠り所になっている。

長男が1歳のとき、新型コロナウイルスが流行した。世界的な大流行で、いつ村で感染が始まるか分からなかった。夫も未曾有の出来事ながら、村で唯一の医師として「村の人を感染させてはいけない」という思いと責任があった。

夜遅くまで情報収集をして村での感染対策を考えていて、1人の背中に村民800人の命が掛かっていた。妻としてできることは、家族が感染しないように対策したり、おいしいご飯を毎日作ることだけだった。ダイニングでパソコンに向かって悩んでいる背中に「がんばれ」と心の中で声を掛けていた。
それからしばらくして、次男を出産した。里帰りをしていたので、村に戻ったのは出産から3ヶ月後のことだった。長男が村に来たときとたまたま同じ月齢だったけれど、コロナが流行る前のようにたくさん抱っこして遊んでもらうことはできなかった。
でも村の人が「孫も、ひ孫も全然村に来れなくて」と、次男は優しく頭を撫でてもらったり何度もアルコール消毒した手で抱きしめてもらって、長男と同じようにたくさん愛情を注いでもらった。

そして長男2歳3ヶ月、次男7ヶ月のときに夫の任期が終わった。幸い、赴任中に村内で感染が広がることはなかったが村を出て1年経った今も新型コロナウィルスが流行している。便利な街に引っ越してきたけど、感染への不安で家にいることが多くなった。気兼ねなく外で子どもを遊ばせられる下北山村の環境はコロナ禍においても恵まれていた。
今も2ヶ月に一度は下北山村に通っている。夫は引き続き村の産業医として関わり、わたしもデザインしたグッズを販売をしているのだ。滞在期間は3日ほどで、めいっぱい下北山村の自然を満喫する。
池神社の周りを散歩したり、下桑原の公園から河原に降りて水遊びをしたり、夜は星空を見ながら夫と焚き火をする。土曜朝市に顔を出して村の人に久しぶりに会うのも毎回楽しみにしている。帰る時はいつも心がホカホカしていて、「明日からまた子育てや仕事をがんばろう」と車の中で夫と笑いながら話している。

子育てをしていて、ふと不安になり心が弱くなるときがある。でも子どもたちが村で受けた愛情を思い出して、「きっといい子に育つ。大丈夫」と自分に言い聞かせる。
子どもたちもいつか、自分の居場所だと思える場所を作ってほしい。世界は意外と広いから、必ず受け入れてくれる場所がある。それがもしも見つからなくてしんどくなってしまったら、仕事を放り投げて、2時間半バスに揺られて下北山村に行ってほしい。胸いっぱいに澄んだ草々の空気を吸い込んで、きなり館で唐揚げ定食をお腹いっぱい食べて、スポーツ公園の草っぱらで昼寝をしたらいい。
君たちの原点はここにあるから。
きっと「おかえり」と言ってもらえるはずだよ。
photo by Togo Yuta , Taguchi Natsumi
- 田口ナツミ
- Taguchi Natsumi

1991年生まれ、大和郡山市在住。京都芸術大学美術工芸学科卒。医師である夫が赴任したことをきっかけに、下北山村で2年間を過ごす。年子兄弟の育児をしながら、透過刺繍の作家として活動している。